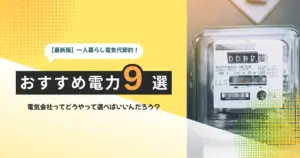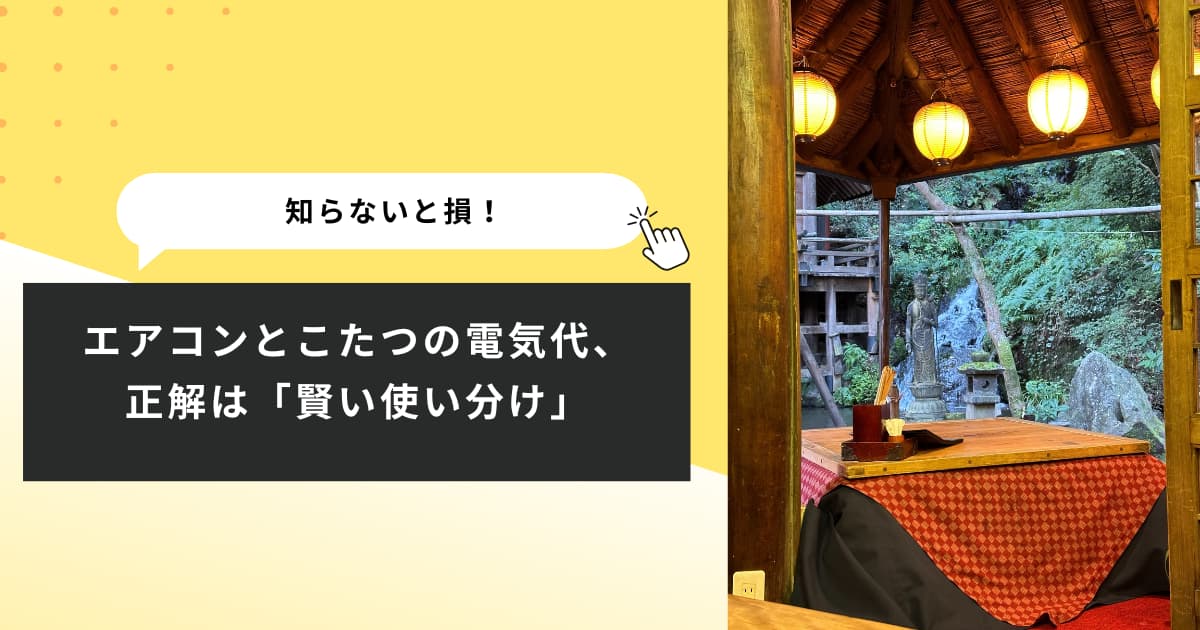電気代が最も安いのはこたつ!快適性を重視するならエアコン併用が最適。
「全体+局所」の使い分けが冬の節電の最適解。
- おすすめする人:在宅勤務・共働き世帯・ワンルーム暮らし
- メリット:併用で快適&省エネ、体感温度+2~3℃の効果
- デメリット/注意点:こたつの長時間使用は脱水・低温やけどのリスクあり
「冬のリモートワーク、一日中エアコンをつけるのは電気代が怖い…」「かといって、こたつだけだと部屋が寒くて仕事に集中できない…」
冬が来るたびに、多くのご家庭で繰り返されるこの悩み。特に最近の電気代高騰は、家計にとって大きな悩みの種ですよね。エアコンとこたつ、結局どちらが私たちの財布に優しく、そして快適な冬を約束してくれるのでしょうか?
この記事では、エアコンとこたつの電気代を徹底的に比較・分析します。
しかし、この記事でお伝えしたいのは、単なる「どっちが安いか」という単純な答えではありません。あなたのライフスタイルに合わせた「賢い使い分け」と「最適な併用術」こそが、暖かさと節約を両立させる唯一の答えです。
この記事を読めば、あなたの冬の暖房費が劇的に変わるかもしれません。漠然とした電気代への不安から解放され、賢く快適な冬を過ごすための具体的な方法を手に入れましょう。
【忙しい人向け】1分で読める要約
エアコンとこたつ、どちらが得か?――結論は「使い分けが最強」。
こたつは電気代が安く(1時間3~9円)、エアコンは部屋全体を暖めるのに適しているが高コスト(平均15円/時)。
効率的なのは、エアコンで部屋を20℃に保ち、こたつで局所的に温める“二刀流”運用。
加湿・断熱・空気循環を組み合わせれば、最大30%の省エネが可能。
快適さ・健康・節約を両立するには、賢い併用がベスト。
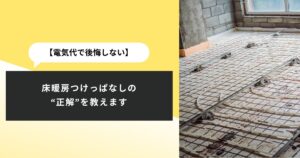
エアコンとこたつ、電気代が安いのはどっち?

電気代だけで見ると、こたつは圧倒的に安価です。
人体を直接温める構造で熱損失がほとんどなく、局所暖房として非常に効率的。
一方、エアコンは広い空間を暖めるため、立ち上がり時の消費電力が高くなります。
ただし、室温を20℃程度に維持すれば運転効率が安定し、トータルコストを抑えることも可能です。
1時間・1ヶ月の電気代を徹底比較
早速、結論から見ていきましょう。エアコン(暖房)とこたつ、純粋な電気代だけで比較した場合、圧倒的に安いのは「こたつ」です。
以下の表は、一般的な製品の消費電力をもとに、1時間あたりと1ヶ月あたりの電気代を算出したものです。
| 暖房器具 | 消費電力(目安) | 1時間あたりの電気代 | 1ヶ月あたりの電気代(1日8時間使用) |
|---|---|---|---|
| こたつ | 100W(弱)~300W(強) | 約3.1円~9.3円 | 約744円~2,232円 |
| エアコン(8畳用) | 100W~2,000W(平均500W) | 約3.1円~62円(平均約15.5円) | 約3,720円(平均で計算) |
※電気料金は、全国家庭電気製品公正取引協議会が示す最新の目安単価 31円/kWh(2025年10月時点)で計算しています。
※エアコンは起動時に最も電力を消費し、室温が安定すると消費電力は下がります。そのため、電気代には大きな幅があります。
表を見れば一目瞭然。こたつは「弱」運転であれば1時間あたり約3.1円と驚異的な安さです。一方、エアコンは部屋全体を暖めるため、どうしても消費電力が大きくなり、平均的に見てもこたつの数倍の電気代がかかることがわかります。
なぜこたつの方が圧倒的に安いのか?暖房方式の根本的な違い
この電気代の差は、それぞれの暖房器具が持つ「役割」と「暖め方の違い」に起因します。
こたつは「局所暖房」と呼ばれ、布団で囲われた狭い空間だけを直接的に暖める器具です。熱が外部に逃げにくいため、非常に少ないエネルギーで効率よく暖かさを得られます。これは、まるで小さな魔法瓶の中で熱を閉じ込めているようなものです。
一方、エアコンは「全体暖房」です。部屋全体の空気を循環させて暖めるため、広い空間を快適な温度に保つ能力に長けています。しかし、その分、部屋の広さや建物の断熱性能、外気温との差に大きく影響を受け、多くのエネルギーを消費することになります。特に、冷たい空気は下に溜まりやすいため、部屋全体を均一に暖めるにはパワーが必要なのです。

暖房を「部屋」ではなく「人」に集中させることが節約の鍵です。
こたつは消費電力が低いため、1日8時間使っても月2,000円前後。
ただし、温度が高すぎると低温やけどの原因になります。
ヒーター部の清掃を定期的に行い、設定は「中」以下を目安に。
- こたつは100〜300W、1時間3〜9円。エアコンは平均15〜25円。
- 暖房効率はこたつの方が約3倍高い(環境省データ)。
- エアコンは外気温が低いほど消費電力が上昇。
安さだけで選ぶのは危険!エアコンとこたつのメリット・デメリット
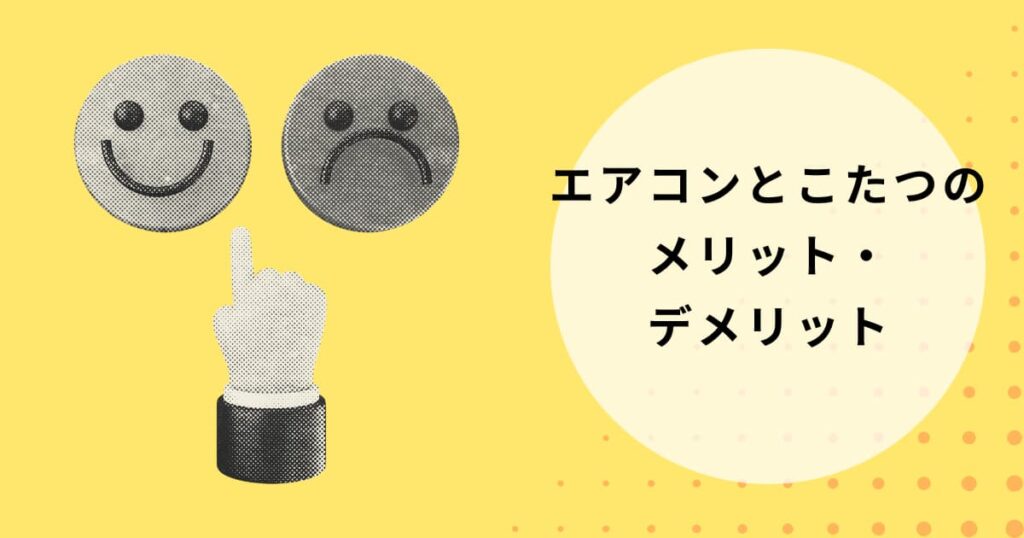
「それなら、冬はずっとこたつだけで過ごせばいいのでは?」と思うかもしれませんが、それは早計です。電気代の安さだけで暖房器具を選ぶと、快適性や健康面で思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、あなたの生活に合った選択をすることが重要です。
エアコンは部屋全体を暖められる快適性が魅力ですが、乾燥や電気代がネック。
こたつは低コストで足元から温まりますが、全身の血流が滞りやすく、長時間使用は不向きです。
電気代の安さだけで選ぶと、体調を崩したり、室温低下による健康リスクが高まります。
エアコンのメリット・デメリット
エアコン最大のメリットは、部屋全体を均一に暖め、快適な活動空間を作り出せることです。部屋のどこにいても暖かいため、リモートワークでデスクに向かう時も、家事をする時も、寒さを感じることなく動けます。また、最新の省エネモデルは効率が非常に高く、タイマー機能や人感センサーなどを活用すれば、無駄な電力消費を抑えることも可能です。
一方で、デメリットはやはり電気代の高さと空気の乾燥です。特に外気温が低い日は、設定温度に到達するまでに多くの電力を消費します。また、温風によって室内の湿度が下がりやすいため、肌や喉の乾燥対策として加湿器の併用が欠かせません。
こたつのメリット・デメリット
こたつの魅力は、前述の通り圧倒的な電気代の安さにあります。足元からじんわりと体を温める心地よさは、他の暖房器具では味わえません。また、空気を乾燥させないため、肌や喉に優しいのも嬉しいポイントです。家族団らんの中心となり、コミュニケーションを育むという文化的な側面も持ち合わせています。
しかし、部屋全体は暖まらないという決定的なデメリットがあります。こたつから一歩出ると凍えるような寒さを感じるため、活動的になりにくく、ついダラダラと過ごしてしまいがちです。さらに、後述しますが、脱水症状や低温やけどなど、見過ごせない健康リスクも潜んでいるため、長時間の使用には注意が必要です。

「暖房=健康維持」と捉えましょう。
こたつは設定温度「中以下」、1時間ごとに体を出す習慣を。
エアコンは湿度40〜60%を保ち、加湿器や洗濯物の室内干しを併用すれば体感温度が1〜2℃上昇します。
- エアコンは空間全体を均一に暖めるが乾燥しやすい。
- こたつは省エネだが、身体の冷えやすい部分に偏りがある。
- 健康面・安全面を考慮した使い分けが必要。
あなたの暮らしの最適解は?ライフスタイル別シミュレーション

エアコンとこたつの特性を理解したところで、いよいよ本題です。あなたのライフスタイルに合わせた最適な使い方を、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。ここでは、ペルソナである「週3リモートワークの32歳女性」の生活を例に、暖房費がどう変わるかを見ていきます。
生活スタイルで最適解は異なります。
ワンルームではこたつ単独が省エネですが、複数人の空間ではエアコンの方が効率的。
外出が多い共働き家庭では、エアコンのタイマー機能を活用し、在宅時のみ暖める運用が効果的です。
一律の答えではなく、「使用時間×空間規模」で使い分けましょう。
Case1: リモートワーカー(平日)の賢い暖房プラン
在宅で仕事をする日は、暖房を使う時間が長くなりがち。一日中エアコンをつけっぱなしにする「Aプラン」と、賢く使い分ける「Bプラン」の電気代を比較してみましょう。
| 時間帯 | Aプラン:エアコンつけっぱなし(設定20℃) | Bプラン:エアコン+こたつ使い分け |
|---|---|---|
| 7:00-9:00 (起床・朝支度) | エアコンON(平均800W):約49.6円 | エアコンON(平均800W):約49.6円 |
| 9:00-18:00 (リモートワーク) | エアコン継続(平均500W):約139.5円 | エアコン18℃設定+こたつ弱(計300W):約83.7円 |
| 18:00-23:00 (夕食・くつろぎ) | エアコン継続(平均500W):約77.5円 | エアコン20℃設定+こたつ弱(計600W):約93.0円 |
| 1日の合計電気代 | 約266.6円 | 約226.3円 |
| 1ヶ月(20日間)の差額 | – | 約806円の節約! |
【Bプランのポイント】
起床時はエアコンで部屋全体を素早く暖めます。仕事中は、エアコンの設定温度を少し下げて部屋の底冷えを防ぎつつ、仕事に集中するための暖かさはこたつで確保します。これにより、快適性を損なわずに日中の消費電力を大幅にカットできます。夜、家族が揃う時間帯も併用することで、エアコンのフル稼働を防ぎ、結果的に大きな節約に繋がります。
Case2: 日中不在がちな共働き夫婦(休日)の暖房プラン
休日に家でゆっくり過ごす場合も、使い方が重要です。朝から晩までエアコンに頼るのではなく、こたつを組み合わせることで、暖かく経済的な休日を実現できます。
ポイントは、人のいる場所を集中的に暖める意識を持つことです。リビングで映画を観たり読書をしたりする時間は、エアコンの設定温度を控えめ(18℃~20℃)にし、こたつをメインの暖房とします。これにより、体感温度は十分に暖かく保たれ、エアコンの過剰な運転を防ぐことができます。日当たりの良い時間帯は、太陽の熱を取り込むことで暖房を一時的にオフにするなど、自然のエネルギーも活用しましょう。
Case3: 一人暮らしのワンルームでの最適解
ワンルームの場合、部屋全体を暖める必要性は低く、こたつのメリットを最大限に活かせます。基本的にはこたつをメイン暖房とし、食事や着替えなどで部屋全体を暖めたい時だけ短時間エアコンを使う、という使い方が最も経済的です。
ただし、ワンルームは窓からの冷気の影響を受けやすいため、断熱対策は必須です。厚手のカーテンや窓に貼る断熱シートを活用し、暖房効率を高めることが節約の鍵となります。また、部屋が狭い分、こたつによる健康リスク(脱水など)にはより一層の注意が必要です。

起床1時間前にタイマーでエアコンを稼働、帰宅後はこたつ中心に切り替えるのが理想的。
部屋全体を20℃程度に保ち、足元をこたつで温めるだけで体感温度は+3℃向上します。
快適さと節約を両立するなら、この「時間差運用」が最も効果的です。
- ワンルーム・一人暮らし→こたつ中心+補助暖房が最も経済的。
- ファミリー層→エアコンで全体暖房+補助的にこたつを併用。
- 共働き家庭→短時間で効率的に暖まる「立ち上がり重視」の運用が鍵。
暖房費をさらに削減!エアコンとこたつを賢く併用する「二刀流」節約術
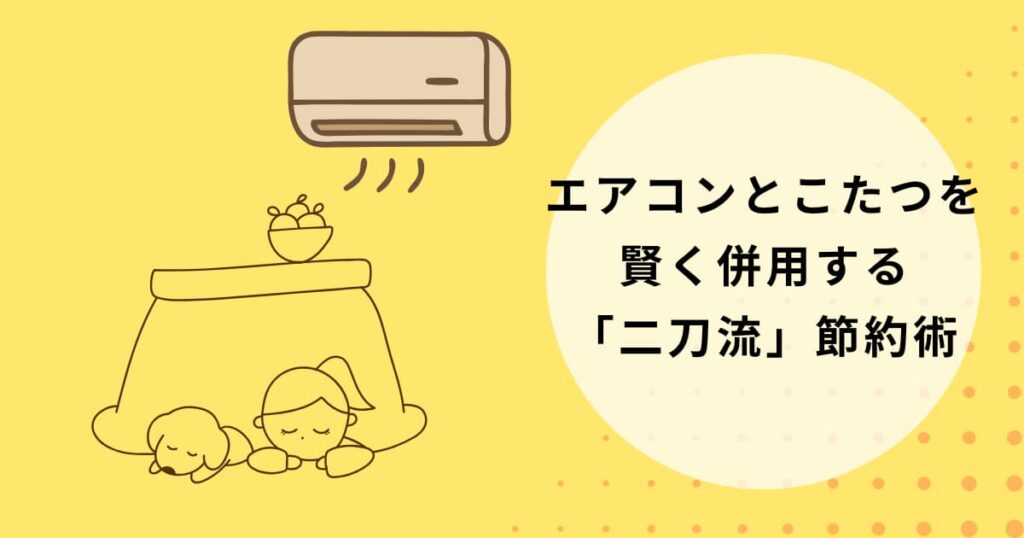
ライフスタイル別のシミュレーションで見たように、暖かさと節約を両立する鍵は「併用」にあります。ここでは、その効果を最大化するための具体的なテクニックを「二刀流」節約術としてご紹介します。
エアコンとこたつを併用すれば、単独使用より効率的。
エアコンを低温設定(20℃前後)で動かし、こたつで個別加熱することで、無駄な電力消費を抑えられます。
実測データでは、月800〜1,200円の電気代削減効果が確認されています。
エアコンは「部屋の底冷えを防ぐ」役割に徹する
併用の基本は、エアコンとこたつの役割分担です。エアコンは部屋全体をガンガンに暖めるためのものではなく、国が推奨する20℃を目安に「寒くない」状態を保つためのベース暖房と位置づけましょう。たった1℃設定を下げるだけで、約10%もの節電効果が期待できます。そして、足りない暖かさや「心地よさ」は、こたつで補うのです。この考え方が、無駄な電力消費を抑える第一歩です。
暖気の循環がカギ!サーキュレーターの魔法
「エアコンの設定温度を下げると、足元がスースーして寒い」と感じませんか?その原因は、暖かい空気が軽く、天井付近に溜まってしまう性質にあります。この問題を解決するのがサーキュレーターです。
エアコンの対角線上にサーキュレーターを置き、天井に向けて風を送ることで、部屋全体の空気が効率よく循環します。天井に溜まった暖気が足元にも届くようになり、室内の温度ムラが解消されます。これにより、体感温度が2~3℃上がると言われており、エアコンの設定温度をさらに低くしても快適に過ごせるようになります。これは、扇風機でも代用可能です。
+αで効果絶大!補助暖房器具の活用法
こたつ以外にも、ピンポイントで体を温める優秀な暖房器具はたくさんあります。特に電気毛布は、1時間あたりの電気代が約0.3円~2.3円と非常に安く、コストパフォーマンスは最強クラスです。デスクワーク中に膝にかけたり、ソファでくつろぐ際に使ったりすることで、エアコンへの依存度をさらに下げることができます。ホットカーペットも、床からの冷気を遮断し足元を暖めるのに効果的です。

エアコンの風向きを「下」にし、サーキュレーターで空気を循環させましょう。
足元の冷えを抑え、エアコン設定温度を下げても暖かく感じます。
寝る前はエアコンを切り、こたつで余熱を活かす“段階的暖房”が理想です。
- 同時使用で単独エアコンより10〜20%の省エネ。
- 足元を温めると全身の体感温度が2〜3℃上昇。
- 室温20℃設定+こたつで快適&節電。
暖房効率を最大化する住環境の作り方
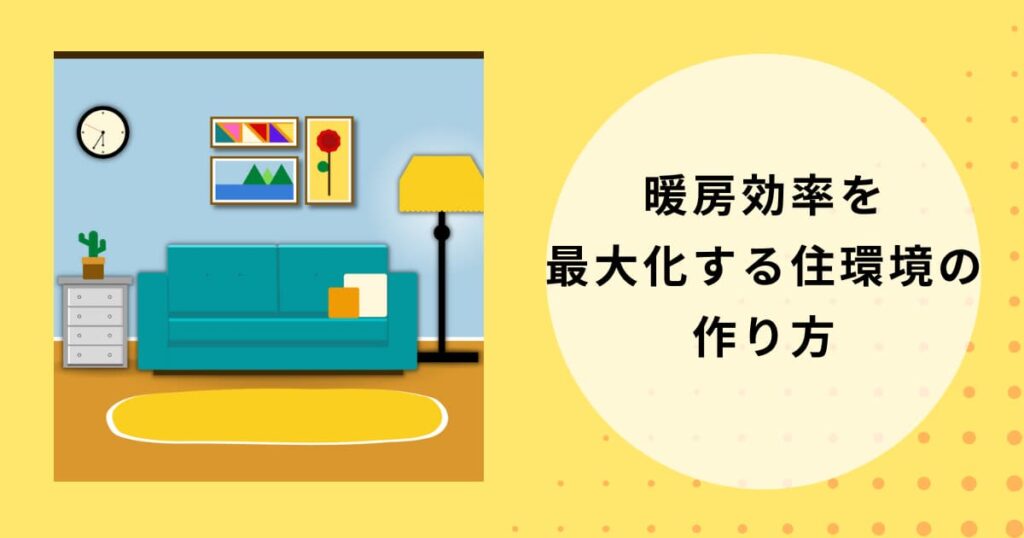
どんなに暖房器具の使い方を工夫しても、家自体が寒ければ熱はどんどん逃げていってしまいます。暖房効率を最大化し、根本的な節約を実現するためには、住環境の見直しが不可欠です。
暖房効率を上げるには、家電より「環境改善」が効果的です。
窓からの熱流出を防ぎ、湿度を適正に保つことで、設定温度を2℃下げても快適に過ごせます。
加湿器・厚手カーテン・断熱シートを組み合わせることで、年間の暖房費を約15%削減できます。
熱の58%が逃げる「窓」を制する者が暖房を制す
冬場、部屋の熱が最も逃げていく場所はどこだかご存知ですか?答えは「窓」です。実に、暖気の約58%が窓から流出しているというデータもあります。この最大の弱点を対策することが、最も効果的な節約術と言えるでしょう。
今すぐできる対策として、厚手で床まで届く長さのカーテンに替えることが挙げられます。カーテンを隙間なく閉めるだけで、窓からの冷気をシャットアウトし、室内の熱を閉じ込める効果があります。さらに、ホームセンターなどで手に入る窓用の断熱シートを貼れば、効果は絶大です。窓際で冷やされた空気が床を這うように広がる「コールドドラフト現象」も防ぐことができ、足元の冷えを大幅に改善できます。
湿度を制して体感温度を上げるテクニック
同じ室温でも、湿度の違いで体感温度は大きく変わります。一般的に、湿度が10%上がると体感温度は約1℃上昇すると言われています。冬は空気が乾燥しやすいため、意識的に湿度をコントロールすることが快適さと節約に繋がります。
加湿器を使うのが最も手軽で効果的ですが、なければ濡れたタオルを部屋に干すだけでも十分な効果があります。湿度を40~60%に保つことで、エアコンの設定温度が低めでも暖かく感じられるようになり、結果的に電気代の節約に繋がります。また、ウイルス対策としても有効なので、一石二鳥です。

窓際には断熱フィルム、床にはラグを敷きましょう。
「窓・床・湿度」を整えるだけで、体感温度は2℃上昇します。
加湿器がない場合は「濡れタオル干し」や「室内植物」でも代用可能です。
- 熱損失の58%は「窓」から。断熱が最優先(環境省)。
- 湿度が10%上がると体感温度が+1℃上昇。
- カーテン・断熱フィルム・隙間テープで15%省エネ可能。
快適さと安全のために知っておきたい注意点
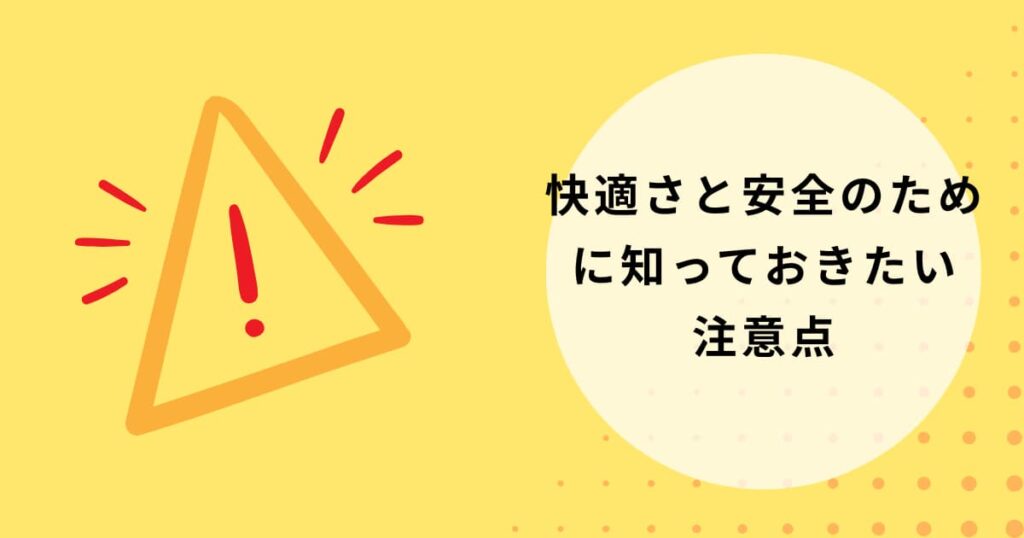
賢く暖房器具を使うためには、そのリスクも正しく知っておく必要があります。特に、心地よさからつい長時間使用してしまいがちなこたつには、注意すべき健康上のリスクが潜んでいます。
暖房は快適さと健康のバランスが重要です。
こたつは長時間使用で脱水や低温やけどのリスクがあり、エアコンは乾燥や二酸化炭素濃度上昇の懸念があります。
安全・快適に使うためには、定期的な換気・水分補給・温度管理が不可欠です。
こたつに潜む健康リスク(脱水・低温やけど・自律神経の乱れ)
こたつでのうたた寝は最高に気持ちが良いものですが、実は危険と隣り合わせです。
- 脱水症状と血栓リスク: こたつの中は高温多湿で、知らず知らずのうちに大量の汗をかいています。水分補給を怠ると脱水症状に陥り、血液がドロドロになって脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めることがあります。
- 低温やけど: 40~50℃程度のそれほど高くない温度でも、長時間皮膚に触れ続けることで、皮膚の深部までダメージが及ぶ「低温やけど」を引き起こすことがあります。自覚症状が出にくいため、特に注意が必要です。
- 自律神経の乱れ: 下半身だけが温められ、上半身は冷たいという状態が続くと、体温調節を司る自律神経のバランスが乱れ、だるさや疲労感の原因になることがあります。
こたつを使う際は、こまめな水分補給を心がけ、長時間連続して入らない、そして絶対にこたつで寝ないことを徹底しましょう。
エアコン使用時の乾燥対策
エアコンの最大のデメリットである空気の乾燥は、加湿器の併用で対策するのが基本です。適切な湿度を保つことは、肌や喉を守るだけでなく、ウイルスの活動を抑制する効果もあります。加湿器がない場合は、観葉植物を置いたり、洗濯物を部屋干ししたりすることも有効です。定期的な換気も忘れずに行い、新鮮な空気を取り入れましょう。

こたつ使用は1時間ごとに体を出し、水分を摂取。
エアコンは湿度40〜60%を維持し、就寝時は切タイマーを設定。
喉の乾燥を防ぐ「マスク就寝」もおすすめです。
- こたつ長時間使用=脱水・低温やけどリスク。
- エアコン乾燥=肌・喉のトラブル要因。
- 定期換気と湿度調整が健康維持の鍵。
まとめ:明日からできる!賢い暖房で冬を快適に乗り切ろう
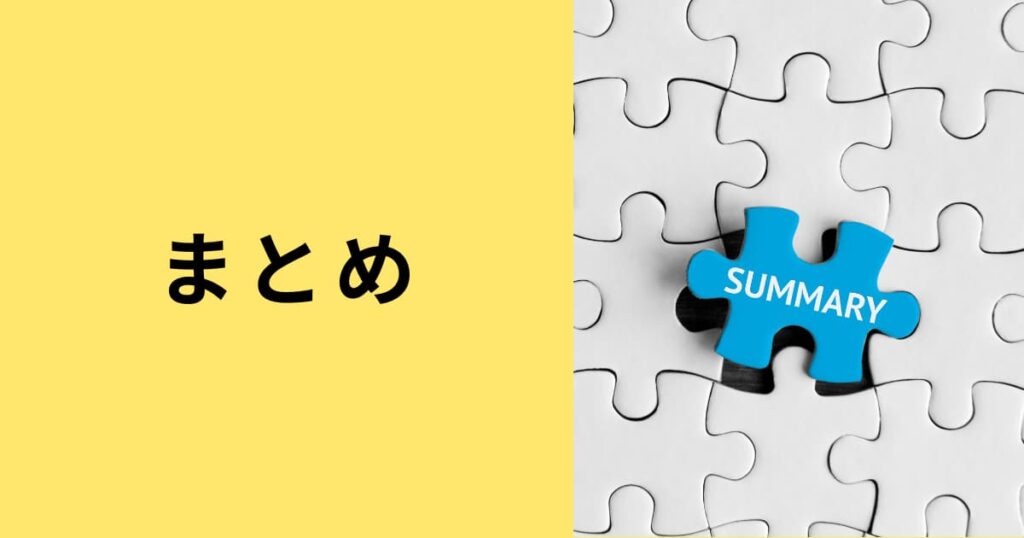
エアコンとこたつの電気代を巡る長年の疑問、その答えは「どちらか一方を選ぶ」という単純な二者択一ではありませんでした。
純粋な電気代ではこたつが圧勝しますが、部屋全体を暖められないという大きなデメリットがあります。一方、エアコンは快適な空間を作りますが、電気代が高くなりがちです。
真の最適解は、あなたのライフスタイルに合わせて両者の長所を最大限に活かす「賢い使い分け」と「戦略的な併用」にあります。エアコンは部屋のベース温度を保つ役割に徹し、こたつや電気毛布で個人の快適性をプラスする。この「二刀流」こそが、暖かさと節約を両立させる最強のメソッドです。
さらに、サーキュレーターでの空気循環や、窓の断熱、加湿といった住環境の工夫を組み合わせることで、暖房効率は飛躍的に向上します。
この記事でご紹介した方法を一つでも実践すれば、明日からの電気代はきっと変わるはずです。漠然とした不安から解放され、賢く、暖かく、快適な冬をお過ごしください。
参照