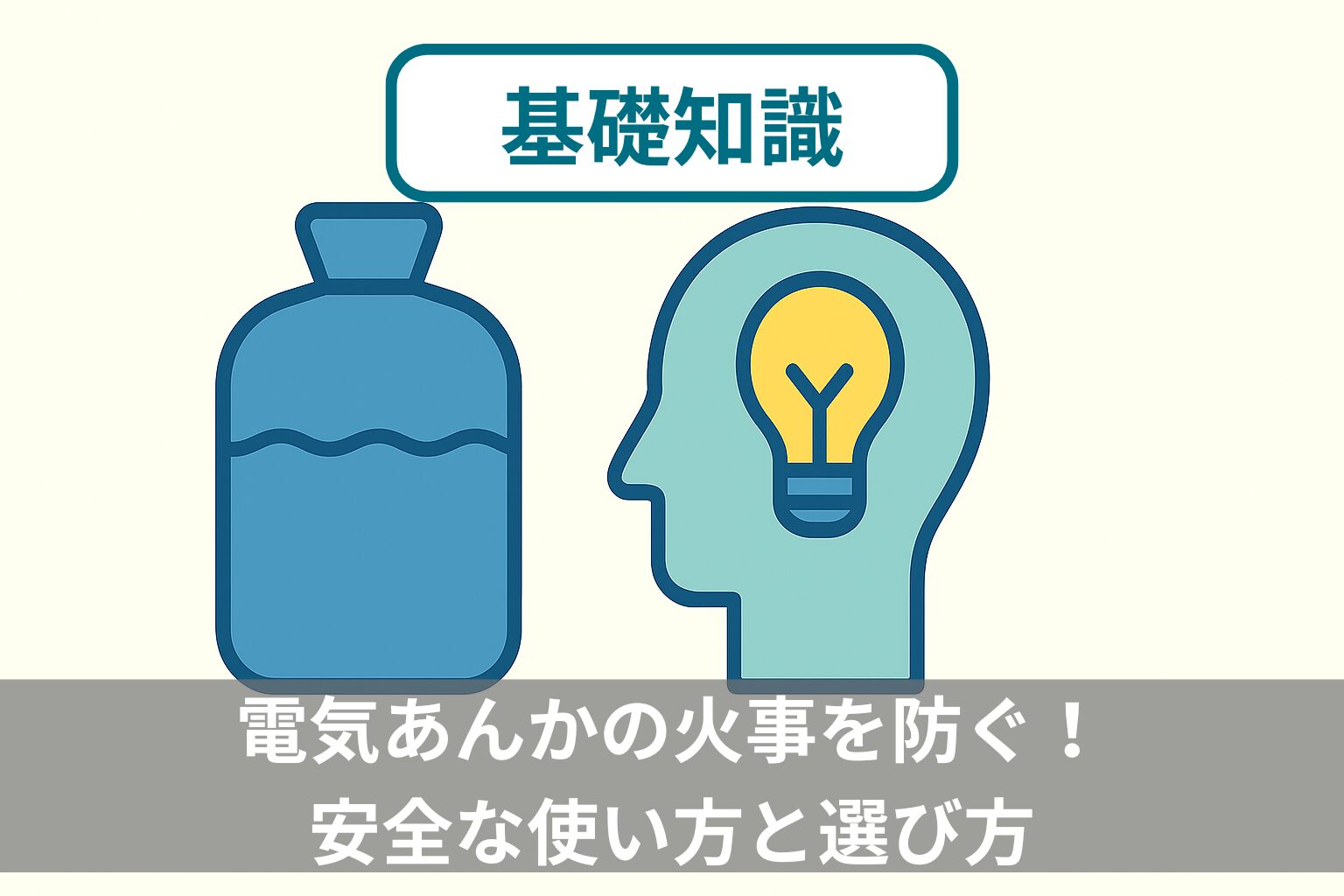冬の寒い夜、足元をじんわりと温めてくれる電気あんか。昔から愛用している方も多く、特にご高齢のご両親にとっては手放せない暖房器具かもしれません。「実家で母が使っている電気あんか、もう何年も同じものだけど大丈夫かしら…」「つけっぱなしで火事になったりしない?」そんな心配をお持ちではありませんか。
その心配は、決して大げさなものではありません。実際に、古い電気あんかや間違った使い方による火災事故は毎年発生しています。しかし、正しい知識を持って、きちんと点検・使用すれば、電気あんかは非常に安全で経済的な暖房器具です。
この記事では、製品評価技術基盤機構(NITE)などの公的機関の情報を基に、電気あんかの火災原因から、今日からすぐに実践できる具体的な予防策、そして安全な製品の選び方までを徹底解説します。大切なご家族とご自身の安全を守るため、ぜひ最後までお読みください。
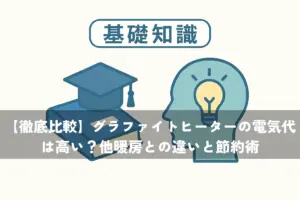
- コードの劣化が火災の主因:見た目に異常がなくても内部断線に注意。
- 使用年数10年以上は要注意:部品の劣化で温度制御が効かなくなり危険。
- 誤使用で発火リスクあり:覆いすぎや逆さ使用で異常加熱が起きやすい。
- 「つけっぱなし就寝」はNG:低温やけど・火災の可能性が高まる。
- 買い替え時は安全機能・PSEマークを必ずチェック。
電気あんかはとても経済的で便利な暖房器具ですが、「コードの劣化」「経年劣化」「誤った使い方」によって火災や低温やけどのリスクがあります。この記事では、火事を未然に防ぐためのチェックリスト付き安全マニュアルと、失敗しない製品選びのポイントが解説されています。特に「10年以上使っている古いあんか」や「就寝時のつけっぱなし」は大変危険。ご高齢の家族が使っている場合は、安全確認と買い替え検討をぜひ。
なぜ起こる?電気あんかの火災、その主な3つの原因
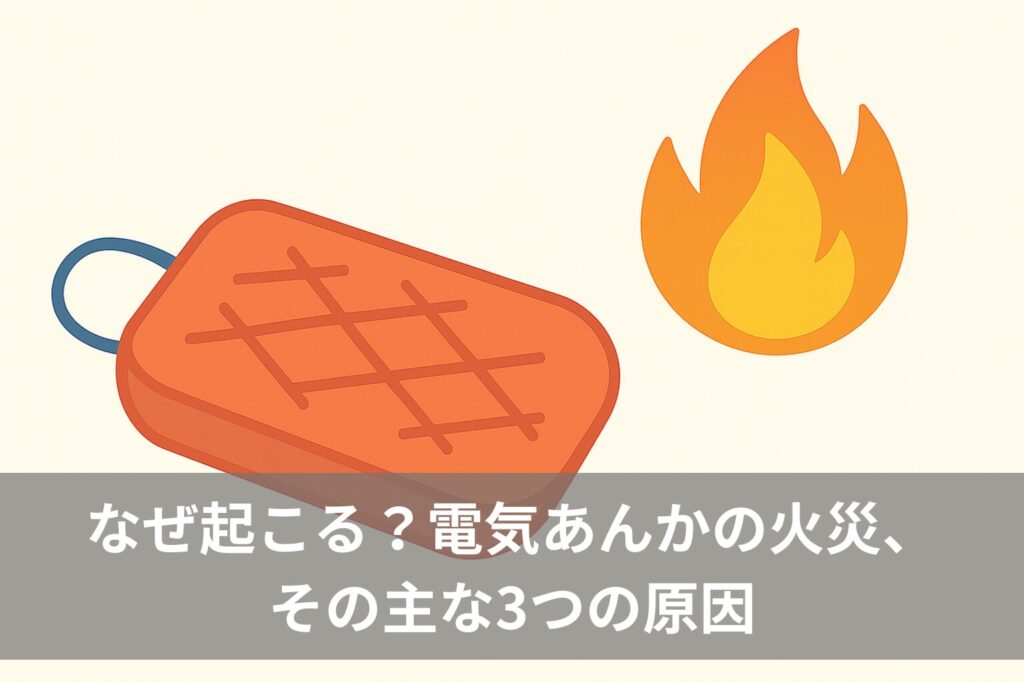
電気あんかによる火災は、決して他人事ではありません。NITE(製品評価技術基盤機構)の報告によると、その原因の多くは「コードの劣化」「経年劣化」「不適切な使用」の3つに集約されます。なぜ火災に至るのか、そのメカニズムを理解することが、予防の第一歩です。
原因1:電源コードの劣化・損傷【最も多い原因】
電気あんかの火災原因として最も多いのが、電源コードの劣化や損傷です。長年使用していると、コードを束ねたり、家具の下敷きにしたり、収納時に折り曲げたりすることで、内部の電線が断線(芯線が切れる)したり、ショート(短絡)したりすることがあります。
特に危険なのが、コードの付け根部分です。抜き差しや使用中の動きで最も負担がかかりやすく、内部で断線が起こりやすい箇所です。見た目には問題がなくても、中で断線しかかっている「半断線」状態になっていると、異常な発熱や火花の発生につながり、布団などの燃えやすいものに引火する恐れがあります。ペットがコードを噛んでしまうケースも、同様に非常に危険です。
原因2:長年の使用による「経年劣化」
「まだ使えるから」と、10年、20年と同じ電気あんかを使い続けていませんか?家電製品には寿命があり、電気あんかも例外ではありません。メーカーが推奨する一般的な寿命の目安は5〜10年とされています。
長期間使用すると、外見に変化がなくても、内部のヒーター線や温度を制御する部品(サーモスタットなど)が劣化します。これらの部品が劣化すると、温度調節が正常に機能しなくなり、異常な高温になって火災を引き起こすリスクが高まります。経済産業省のデータでも、10年以上使用した古い製品による事故が多く報告されており、注意が必要です。
原因3:意外と知らない「不適切な使い方」
電気あんかは手軽に使える反面、使い方を誤ると危険です。例えば、「もっと暖かくしたい」と電気あんかを布団や毛布で幾重にも覆ってしまうと、熱がこもりすぎて異常な高温になることがあります。これにより、あんか本体が溶けたり、布団が炭化して発火したりする「くすぶり火災」につながる危険性があります。
また、電気あんかを立てかけたり、裏返して使ったりするのもNGです。内部の熱が均一に分散されず、特定の部分だけが高温になる「ホットスポット」ができてしまい、そこから発火する可能性があります。取扱説明書に記載された正しい使い方を守ることが、安全への近道です。
【事故事例】NITEに報告された実際の火災ケース
実際に起きた事故例を知ることで、危険性をより身近に感じることができます。
- ケース1:就寝中に電気あんかを使用していたところ、電源コードが家具の下敷きになっていたため、コードが押しつぶされてショート。布団に着火し、火災に至った。
- ケース2:15年以上使用していた古い電気あんかをつけっぱなしで就寝。経年劣化により温度調節機能が故障し、異常な高温になったことで低温やけどを負い、さらに布団が焦げて発火した。
- ケース3:電気あんかの電源コードをきつく束ねたまま使用したため、コードが異常発熱して被覆が溶け、ショートして火災になった。
これらの事故は、いずれも日頃のちょっとした注意で防げた可能性が高いものです。ご自宅の電気あんかは大丈夫か、次の章のチェックリストで確認してみましょう。

古い製品やコードに少しでも違和感を感じたら、即点検・買い替えを。
- コードの曲げ・圧迫・束ね使用は絶対NG。
- 製品寿命(5〜10年)を意識しよう。
- ペットがいる家庭は特に要注意。
これで安心!今日から始める電気あんか安全マニュアル【チェックリスト付】
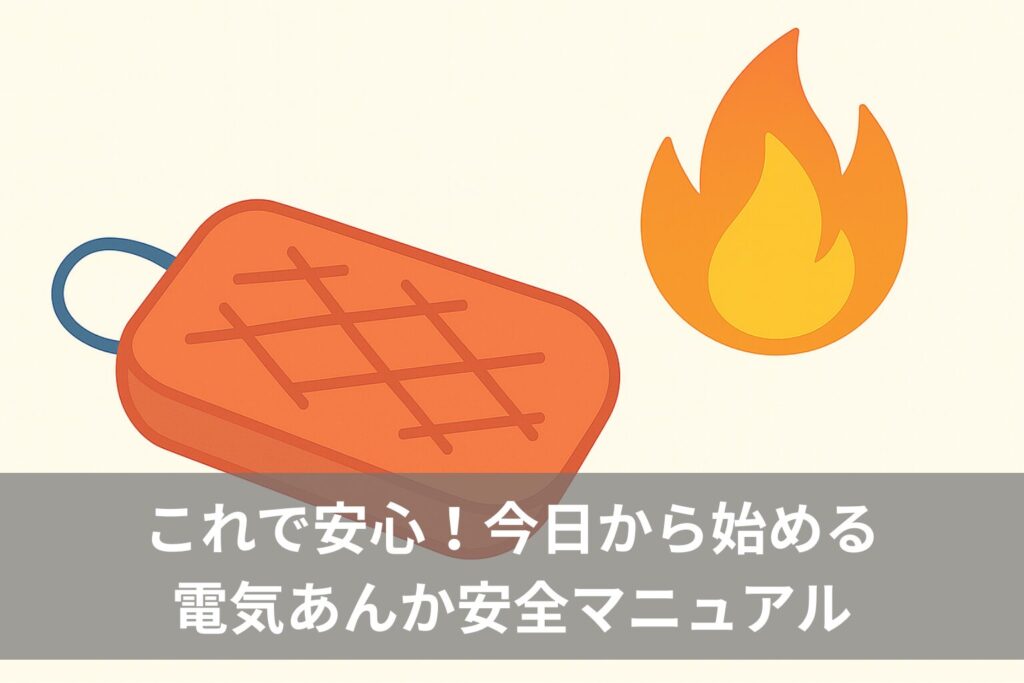
電気あんかの事故を防ぐためには、「使う前」「使っている時」「使い終わった後」の各段階でのチェックが重要です。ご自宅やご実家の電気あんかをこのリストに沿って点検し、安全に使用しましょう。
【使用前】シーズン初めの安全チェックリスト
冬になり、久しぶりに電気あんかを押し入れから出す際には、必ず以下の点を確認してください。一つでも異常があれば、その製品の使用は中止してください。
「寿命かも?」買い替えを検討すべき危険な5つのサイン
チェックリストの項目に加え、以下のようなサインが見られたら、それは電気あんかの寿命が近づいている証拠です。重大な事故につながる前に、速やかに買い替えを検討してください。
- 異音・異臭がする: 使用中に「ブーン」という低い音や「チリチリ」という音が聞こえたり、プラスチックやゴムが焼けるような焦げ臭いにおいがしたりする場合は、内部の部品が異常をきたしている可能性が高いです。直ちに使用を中止し、コンセントからプラグを抜いてください。
- 温度が異常: 電源を入れてもなかなか温まらない、あるいは逆に触れないほど熱くなるなど、温度調節が不安定な状態は非常に危険です。サーモスタットの故障が考えられます。
- 電源がついたり消えたりする: コードを少し動かしただけで電源が入ったり切れたりする場合、コード内部が断線しかかっている(半断線)状態です。いつショートして火花が出てもおかしくありません。
【使用中】火事を防ぐ正しい使い方5つのルール
安全に使うためのルールは、決して難しくありません。毎日の習慣にしましょう。
- 就寝時は電源を切るのが基本: 就寝前に布団を温め、眠るときには電源を切るのが最も安全です。つけっぱなしで寝ると、低温やけどのリスクに加え、万が一の故障時に火災に気づくのが遅れる危険があります。タイマー機能付きの製品なら、寝る前にセットしておくと安心です。
- コードはゆったりと: コードを束ねたり、ねじったり、家具や布団の重みで圧迫したりしないでください。熱がこもったり、断線の原因になったりします。
- あんかの上には何も置かない: 電気あんかの上に、枕やクッション、分厚い毛布などを重ねて置かないでください。放熱が妨げられ、異常な高温になる原因となります。
- 直接肌に触れさせない: 必ずタオルや布で包むか、体から少し離して使いましょう。低温やけどを防ぐためです。(低温やけどについては後ほど詳しく解説します)
- ペットには使わない: 犬や猫はコードを噛んでしまったり、熱くても同じ場所で寝続けて低温やけどを負ったりする危険があります。ペットにはペット専用のヒーターを使いましょう。
【シーズンオフ】来年も安全に使うための正しい保管方法
シーズンが終わり、電気あんかをしまう際にも一手間かけることで、来年も安全に使えます。
- ホコリをきれいに拭き取る: 本体やコードに付着したホコリは、湿気を吸って故障やトラッキング火災の原因になります。乾いた布で優しく拭き取りましょう。
- コードはゆるく巻く: コードを本体にきつく巻きつけたり、きつく折りたたんだりするのは断線の原因になります。購入時のように、ゆるく円を描くように束ねましょう。
- 上に物を置かない: 押し入れの奥などにしまう際、上に重いものを載せないでください。本体の破損やコードの断線につながります。
- 湿気の少ない場所に保管: 湿気は電子部品の大敵です。ビニール袋などに入れて、乾燥した場所に保管してください。

季節の変わり目には点検を「習慣化」すると安心です。
- 焦げ臭い・異音は即使用中止。
- コードは“ゆるく束ねて”“湿気を避けて”保管。
- 異常に気づいたら“買い替えが最善”。
もう迷わない!安全な電気あんかの選び方【3つのポイント】

ご両親へのプレゼントや、自宅の古い電気あんかを買い替える際には、価格やデザインだけでなく「安全性」を最優先に選びましょう。チェックすべきポイントは3つです。
ポイント1:絶対条件!「安全機能」をチェック
最近の電気あんかには、万が一の事故を防ぐための重要な安全機能が搭載されています。以下の機能は必ず確認しましょう。
- 温度過昇防止機能(サーモスタット): これはいわば「見張り番」です。電気あんかが布団の中で熱がこもるなどして設定以上に温度が上がった場合、自動で電源をオフにしたり、温度を下げたりしてくれます。 ほとんどの製品に搭載されていますが、万が一の時に命を守る重要な機能です。
- 温度ヒューズ: サーモスタットが万が一故障してしまっても、さらに温度が上がり続けた場合に、最終的な安全装置として回路を物理的に遮断するのが温度ヒューズです。これが作動すると製品は使えなくなりますが、火災という最悪の事態を防いでくれます。
ポイント2:信頼の証「PSEマーク」を確認しよう
家電製品の購入時に必ず確認したいのが「PSEマーク」です。これは、日本の電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。このマークがない製品は、国内での販売が法律で禁止されています。
PSEマークにはひし形と丸型の2種類がありますが、電気あんかは「丸形PSE」の対象製品です。海外製の安価な製品などにはPSEマークがないものも紛れている可能性があるため、購入時には必ず本体やパッケージを確認しましょう。
ポイント3:使い方に合わせた「形状」と「機能」を選ぶ
安全機能を確認したら、次は使いやすさを考えましょう。電気あんかには主に3つの形状があります。
| 形状 | 特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 平形 | 最もオーソドックスな板状のタイプ。布団の中で邪魔になりにくく、足元全体を広くじんわり温める。 | シンプルなものを好む方、寝返りをよくうつ方。 |
| 山形(かまぼこ形) | 中央が盛り上がった形状。布団との間に空間ができ、熱がこもりにくく、通気性が良い。足先をピンポイントで温めたい場合に。 | 足先の冷えが特につらい方、熱のこもりが気になる方。 |
| ソフトタイプ | 布製で柔らかく、体にフィットしやすい。湯たんぽのような感覚で使える。腰やお腹など、足元以外にも使いたい場合に便利。 | いろいろな場所で使いたい方、柔らかい感触が好きな方。 |
さらに、「温度調節機能」が付いていると、その日の気温や体調に合わせて細かく温度を変えられるので非常に便利です。特に、皮膚感覚が変化しやすいご高齢の方が使う場合は、低温に設定できるモデルを選ぶとより安心です。

ご両親や祖父母へのプレゼントなら、「安全機能」と「柔らかさ」の両方を重視しましょう。
- 「丸形PSEマーク」が安心の証。
- 温度調整機能付きは高齢者や子どもにもおすすめ。
- 平形・山形・ソフト型など使用部位に合わせた選択を。
火事だけじゃない!電気あんかに潜む「低温やけど」のリスク

「熱湯じゃないから大丈夫」と思いがちですが、電気あんかには「低温やけど」という深刻なリスクが潜んでいます。
なぜ危険?低温やけどの仕組みと症状
低温やけどとは、体温より少し高いくらいの温度(44℃~50℃程度)のものに、皮膚が長時間触れ続けることで起こるやけどです。熱いと感じにくいため気づきにくく、じっくりと皮膚の奥深くまでダメージが進行してしまうのが特徴です。
見た目は少し赤くなっているだけ、ヒリヒリする程度でも、皮膚の深い部分では細胞が壊死している場合があります。特に、糖尿病で血行障害がある方や、皮膚が薄い高齢者・乳幼児は感覚が鈍いこともあり、重症化しやすいので最大限の注意が必要です。
低温やけどを防ぐための具体的な対策
低温やけどは、正しい使い方で予防できます。
- 就寝時は体から離すか電源OFF: 最も効果的なのは、寝る前に布団を温めておき、就寝時には電源を切ることです。もしつけたまま寝る場合は、必ず足元など体から離れた場所に置きましょう。
- 直接肌に触れさせない: 必ず厚手のタオルや専用のカバーで包んで使いましょう。肌とあんかの間に一層クッションを設けることが大切です。
- タイマー機能を活用する: 1〜2時間で切れるようにタイマーを設定すれば、寝入った後の長時間の接触を防げます。
- 時々、位置を変える: 同じ場所にずっと当て続けないよう、意識的にあんかの位置を変えることも有効です。
もし低温やけどをしてしまったら?応急処置の方法
万が一、皮膚に赤みやヒリヒリ感、水ぶくれができてしまった場合は、すぐに以下の処置を行ってください。
- すぐに冷やす: まずは電気あんかの使用を中止し、患部を清潔な流水で15〜20分ほど冷やします。氷や保冷剤を直接当てるのは、刺激が強すぎるため避けてください。
- 水ぶくれは潰さない: 水ぶくれは、外部の細菌から傷口を守る役割があります。自分で潰さず、清潔なガーゼなどで保護しましょう。
- 速やかに皮膚科を受診する: 低温やけどは見た目より重症なことが多いです。自己判断で薬を塗ったりせず、必ず専門医の診察を受けてください。

皮膚が弱い方は「温度調節機能+自動OFFタイマー付モデル」が最適です。
- 就寝時のつけっぱなしは絶対NG。
- 厚手の布で包む+タイマー活用が基本。
- 特に高齢者・乳幼児・糖尿病患者は要注意。
電気あんかの気になるQ&A

ここでは、電気あんかに関するよくある質問にお答えします。
電気代はどのくらいかかるの?
電気あんかは、他の暖房器具と比較して非常に電気代が安いのが大きなメリットです。製品にもよりますが、1時間あたりの電気代は約0.1円~0.5円程度。一晩(8時間)つけっぱなしにしても数円程度で済む計算になります。エアコンや電気ストーブと比べると、その経済性は明らかです。
| 暖房器具 | 1時間あたりの電気代(目安) |
|---|---|
| 電気あんか | 約0.1円~0.5円 |
| 電気毛布 | 約0.5円~2円 |
| こたつ(弱) | 約2円~5円 |
| エアコン(暖房) | 約3円~62円 |
※電気料金単価31円/kWhで計算した場合の目安
電気毛布との併用は大丈夫?
電気あんかと電気毛布の併用は、過熱の危険性が高まるため推奨されません。 暖房器具はそれぞれ単独で使用することを前提に安全設計がされています。両方を同時に使用すると、熱がこもりすぎてしまい、温度制御機能がうまく働かなくなる可能性があります。どちらか一方を使用するようにしてください。
ペット(犬・猫)に使ってもいい?
ペットへの使用は避けてください。 犬や猫は自分で熱さを調節できず、同じ場所で寝続けて低温やけどを負う危険があります。また、コードを噛んで感電したり、火災を引き起こしたりする事故も報告されています。ペットには、コードが保護されていたり、温度設定が低めに作られていたりするペット専用のヒーターやマットを使用してください。
古い電気あんかの処分方法は?
電気あんかは「小型家電リサイクル法」の対象品目に含まれることが多いです。処分の際は、まずお住まいの自治体のルールを確認してください。多くの自治体では、市役所や公共施設に設置された「回収ボックス」に入れるか、「不燃ごみ」または「小型家電」として指定の日に出すよう定められています。正しい方法で処分しましょう。
まとめ
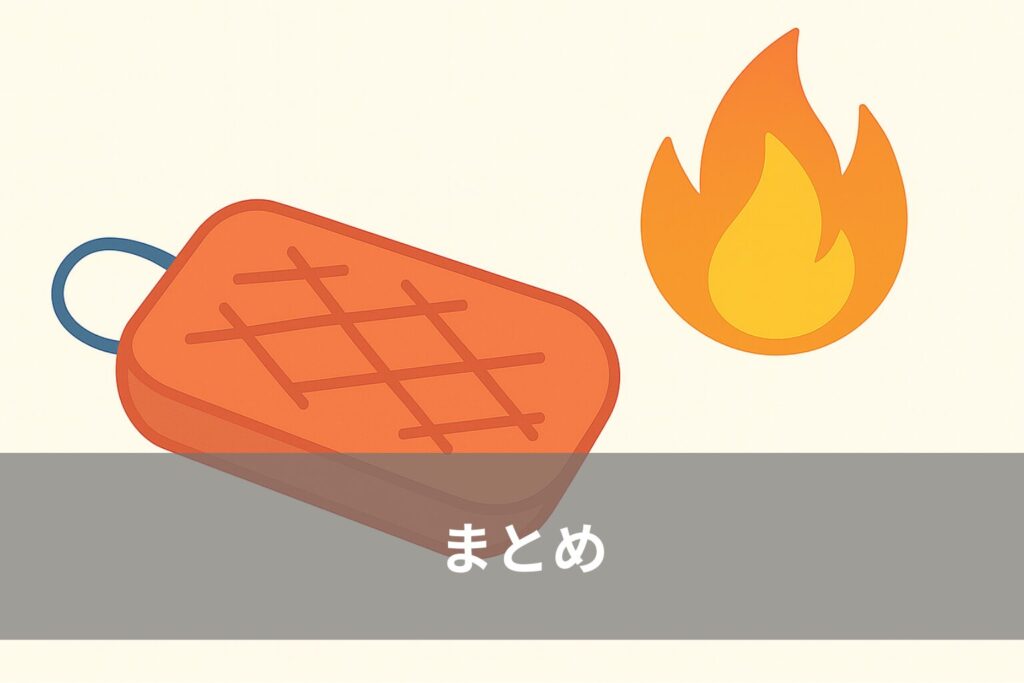
電気あんかは、手軽で経済的に体を温めてくれる便利なアイテムですが、その手軽さゆえに危険性が見過ごされがちです。しかし、この記事でご紹介したように、火災や低温やけどのリスクは、正しい知識と少しの注意で確実に防ぐことができます。
特に重要なのは、「電源コードに異常がないか定期的にチェックする」「つけっぱなしで寝ない」「寿命(5~10年)を意識し、異常があればすぐに使用をやめる」という3点です。
ご自身が使う場合はもちろん、離れて暮らすご家族が使っている電気あんかが気になる場合は、ぜひこのページのチェックリストを手に、一度点検してあげてください。安全な製品へ買い替えることも、大切な家族を守るための素晴らしいプレゼントになります。正しい使い方で、安全で暖かい冬をお過ごしください。