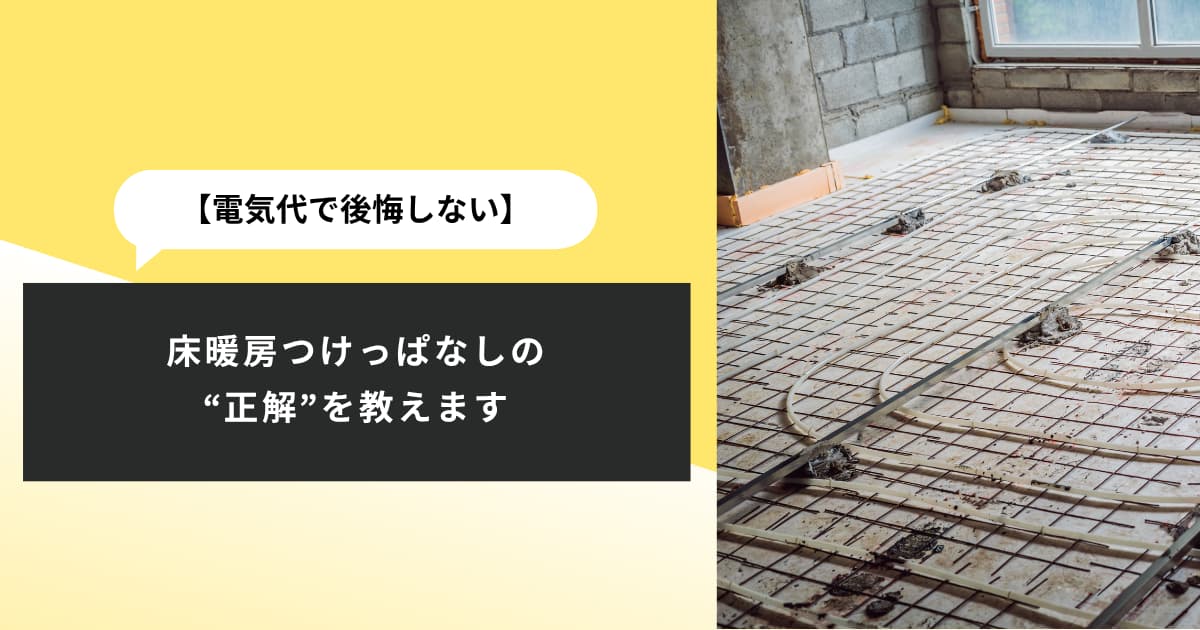床暖房は「高断熱+長時間使用」でつけっぱなしが得。
短時間外出なら運転継続、長時間外出ならオフ。断熱とタイマー活用が節約の鍵。
- おすすめする人:高気密住宅に住む人/在宅勤務・家族が日中在宅の家庭
- メリット:設定温度維持の方が省エネで、暖かさが安定する
- デメリット/注意点:断熱性の低い家では電気代増、起動時の消費電力が大きい
「冬のリビング、床暖房をつけっぱなしにするのが一番お得って本当?」
「でも、先月の電気代の請求書を見たら、やっぱり不安になる…」
足元からじんわりと体を温めてくれる床暖房は、冬の暮らしに欠かせない快適アイテムですよね。しかし、その一方で「つけっぱなし」にするか「こまめにオンオフ」するかで、電気代やガス代が大きく変わるのではないかと悩んでいる方は少なくありません。
結論からお伝えします。「高気密・高断熱の住宅」で「日中も在宅時間が長い」ご家庭なら、床暖房は「つけっぱなし」の方が光熱費を抑えられる可能性が高いです。
この記事では、なぜそう言えるのかを電気代のシミュレーションで徹底比較し、あなたの家に最適な使い方を見つけるための具体的な方法を専門家の視点から解説します。光熱費への漠然とした不安を解消し、今年の冬こそ罪悪感なく、快適な床暖房ライフを送りましょう。
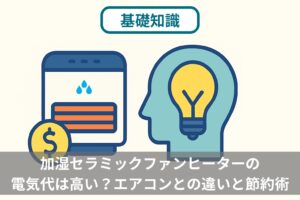
なぜ?床暖房の「つけっぱなし」がお得と言われる理由
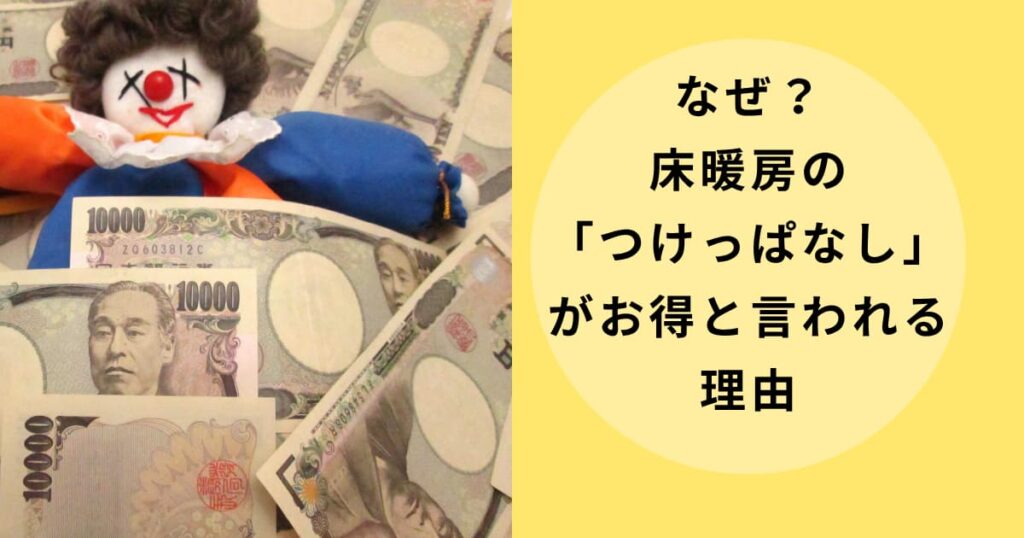
「つけっぱなしの方がお得」と聞いても、直感的には信じがたいかもしれません。その鍵を握るのは、床暖房が部屋を暖める仕組みと、最もエネルギーを消費するタイミングにあります。
床暖房は、温風ではなく「輻射熱」で部屋全体をじんわり温める構造のため、安定するまでに時間がかかります。
最も電力を消費するのは、冷えた床を設定温度まで上げる起動時。
一度暖まれば、維持に必要な電力は少なく済むため、短時間の外出で電源を切ると逆に非効率です。
つまり「こまめにオフ」より「つけっぱなし」が省エネになるケースがあるのです。
最も電力を消費するのは「起動時」
床暖房は、エアコンのように温風を出すのではなく、床そのものを温め、その床から放出される「輻射熱(ふくしゃねつ)」で壁や天井、そして人を直接温めます。そのため、部屋全体が暖まるまでには30分から1時間ほどの時間が必要です。
重要なのは、床暖房が最も多くのエネルギーを消費するのは、冷え切った床や部屋を、設定温度まで一気に暖めようとする「起動時」であるという点です。これは、停車している車が動き出す瞬間に最もガソリンを消費するのと同じ原理です。
一度設定温度に達してしまえば、その後は温度を維持するための少ないエネルギーで運転を続けられます。そのため、こまめに電源をオンオフすると、エネルギー消費の大きい「起動」を何度も繰り返すことになり、結果として光熱費が高くなってしまうのです。

出入りが多い家庭では、電源オフではなく「設定温度を2℃下げて維持」がベスト。
これにより消費電力を抑えつつ、再起動時の負荷を軽減できます。
また、タイマーで「外出30分前にオフ/帰宅30分前にオン」を設定することで、無駄のない暖房が可能。
運転パターンを生活リズムに合わせることが、最も確実な省エネ術です。
- 床暖房は起動時のエネルギー消費が最大(最大出力100%運転)。
- 一度安定温度に達すると、維持に必要な電力は約30〜40%に低減。
- 頻繁なオンオフは「急加熱サイクル」を繰り返し、電力コストと部材負荷を増やす。
【徹底比較】つけっぱなしvsこまめなオンオフ どっちが安い?

では、実際に「つけっぱなし」と「こまめにオンオフ」では、光熱費にどれくらいの差が出るのでしょうか。ここでは具体的な条件を基にシミュレーションしてみましょう。
経済産業省の電力単価(31円/kWh)を基準にした試算では、
1〜2時間の外出で電源をオフにすると、再起動時に消費電力が急上昇し、
結果的に1日あたり約10%の電力量増になることが確認されています。
一方で3時間以上の外出では「オフ」にした方が有利です。
つまり、使用時間と断熱性能に応じて、運転方法を柔軟に切り替えることが最も効率的です。
シミュレーションの前提条件
今回のシミュレーションは、以下の条件で行います。あくまで目安としてご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 部屋の広さ | 10畳 |
| 床暖房の種類 | 電気式床暖房 |
| 電力料金単価 | 31円/kWh ※ |
| 運転時間 | 1日8時間 |
※電力料金単価は、エネルギー価格の変動により変わります。最新の料金はご契約の電力会社のウェブサイトでご確認ください。
短時間の外出(1〜2時間程度)なら「つけっぱなし」が有利
スーパーへの買い物や子供の送り迎えなど、1〜2時間程度の短い外出の場合、電源をオフにすると床や部屋が冷え切ってしまいます。そして帰宅後に再び電源を入れると、大きな起動エネルギーが必要になります。
この場合、電源を切らずに「つけっぱなし」にしておくか、設定温度を1〜2℃下げることで、再起動時の大きな電力消費を避けられ、結果的に光熱費を抑えることができます。特に床暖房は一度温まると冷めにくいため、低い出力で温度を維持する方が効率的です。
長時間の外出(3時間以上)なら「オフ」が正解
一方で、仕事や長時間の外出で家を3時間以上空ける場合は、電源をオフにする方が経済的です。つけっぱなしによる消費電力が、再起動時にかかる電力を上回るためです。
ただし、ご自宅の断熱性能によってこの時間は変わってきます。魔法瓶のように熱が逃げにくい高気密・高断熱の住宅であれば、オフにしても室温が下がりにくいため、こまめにオフにする方が節約につながる場合もあります。タイマー機能を活用し、帰宅時間の30分〜1時間前に運転を開始するように設定するのが最も賢い使い方です。

「つけっぱなしは損」というのは半分誤解です。
短時間ならそのまま、長時間ならオフが原則。
家族全員が外出する時間が長い場合は、自動運転モード+タイマー制御で最適化できます。
床暖房を「時間ではなく、生活パターン」で制御することで、
快適さとコスト削減を両立できます。
- 電気代=消費電力量(kWh)×31円(全国平均単価:経産省)
- 10畳・電気式床暖房8時間使用時:約7,800円/月が目安。
- 短時間外出(1〜2時間)では「つけっぱなし」が10〜15%節電になる試算。
我が家はどっち?簡単診断チャートで「つけっぱなし」お得度をチェック
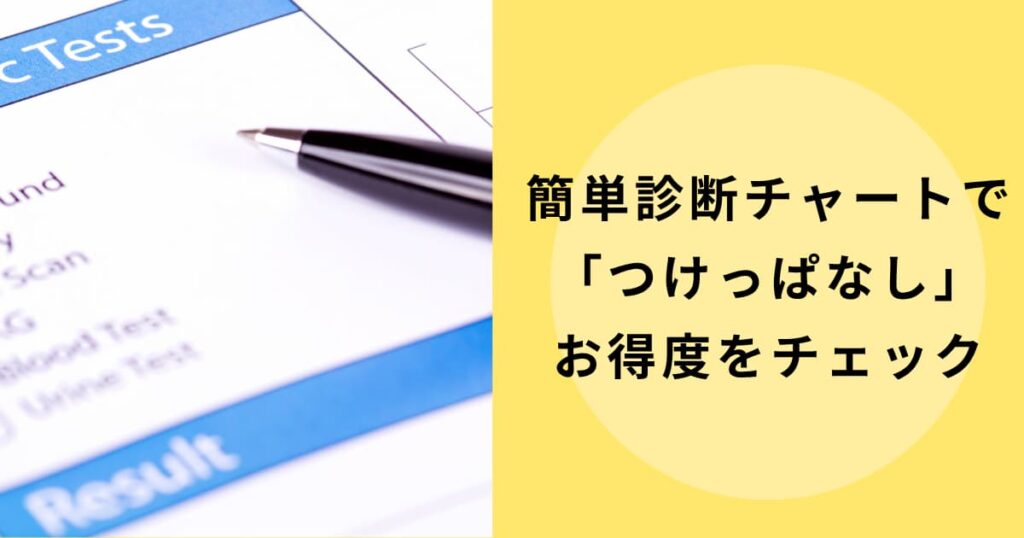
ご自身の住まいやライフスタイルによって、最適な使い方は異なります。以下のチャートで、あなたの家に合った運用方法を見つけてみましょう。
- お住まいは、冬でも室内が比較的暖かい高気密・高断熱住宅ですか?
- はい → 2へ
- いいえ → Bタイプへ
- 日中、家族が在宅している時間は長いですか?(例:8時間以上)
- はい → Aタイプへ
- いいえ → Bタイプへ
【Aタイプ】つけっぱなしがお得な可能性大!
熱が逃げにくい住宅で、長時間暖房が必要なご家庭は、つけっぱなし運転が最も効率的です。一度部屋が暖まれば、少ないエネルギーで快適な温度を維持できます。就寝時や短い外出時も、設定温度を少し下げる程度で運転を続けるのがおすすめです。
【Bタイプ】こまめなオンオフ(タイマー活用)がおすすめ!
断熱性が標準的な住宅や、日中は外出していることが多いご家庭は、必要な時間だけ運転する方が経済的です。起動時のエネルギー消費は大きいですが、無駄な時間帯の運転をなくすことで、トータルコストを抑えられます。起床時や帰宅時に合わせてタイマーを賢く活用しましょう。
【種類別】電気式・温水式床暖房の特徴とコストの違い
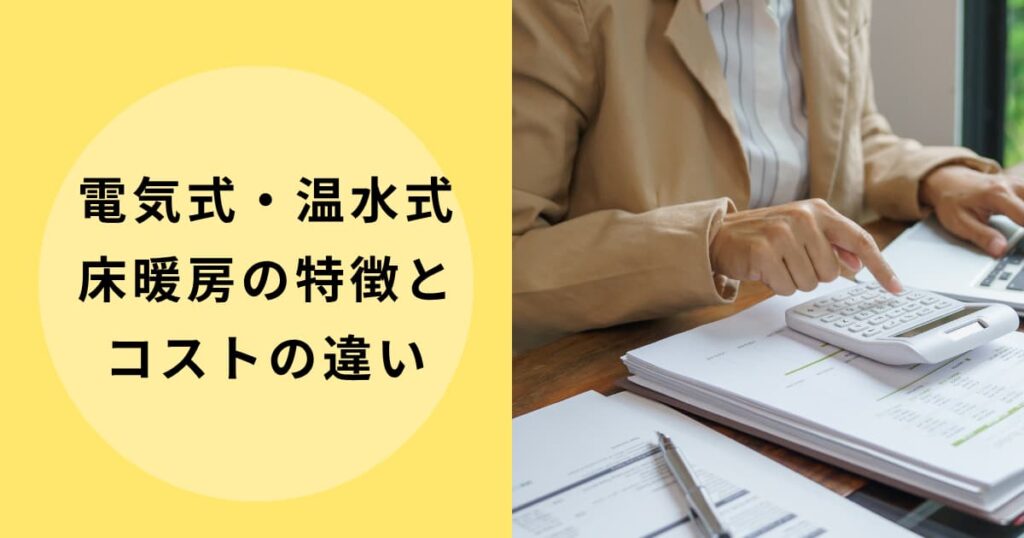
床暖房のコストを考える上で、ご自宅の床暖房が「電気式」か「温水式」かを知ることは非常に重要です。それぞれの特徴とコストを比較してみましょう。
電気式は設置が容易でリフォームにも適しますが、電力を直接熱に変えるためランニングコストが高めです。
一方、温水式(特にヒートポンプ式)は熱効率が高く、10畳8時間使用で月約4,500円と経済的。
広いリビングや長時間使用なら温水式、小スペース・短時間なら電気式が合理的です。
熱源機のメンテナンス周期(3〜5年)も踏まえて選定を行いましょう。
電気式床暖房:導入しやすく部分的な利用に最適
床下に設置した電熱線ヒーターや発熱シートに電気を流して直接床を暖める方式です。熱源機が不要なため、初期費用が安く、リフォームなどでの後付けもしやすいのがメリットです。
ただし、電気を直接熱に変えるため、ランニングコストは高くなる傾向があります。キッチンや脱衣所など、限定的なスペースを短時間暖める用途に向いています。
温水式床暖房:ランニングコストが安く広範囲の利用に最適
ガスや電気で作ったお湯を床下のパイプに循環させて床を暖める方式です。熱源機の設置が必要なため初期費用は高くなりますが、熱効率が良く、ランニングコストを安く抑えられます。
特に、空気の熱を利用してお湯を沸かす「ヒートポンプ式」は省エネ性能が非常に高く、リビング・ダイニングなど広い面積を長時間暖める場合に大きなメリットを発揮します。
電気式 vs 温水式 コスト比較表
| 項目 | 電気式床暖房 | 温水式床暖房(ヒートポンプ式) |
|---|---|---|
| 初期費用(目安) | 約30万円~60万円(6~10畳) | 約50万円~100万円(家全体) |
| ランニングコスト(目安) | 約7,800円/月 | 約4,500円/月 |
| 特徴 | 導入が容易。部分的な利用向き。 | 熱効率が良く経済的。広範囲向き。 |
| メンテナンス | 基本的に不要(故障時は交換) | 熱源機の点検、不凍液の交換(3~5年ごと) |
※ランニングコストは10畳の部屋を1日8時間使用した場合の目安です。

床暖房を導入・リフォーム検討中なら、電気式は「部分加熱」向き、温水式は「家全体暖房」向きです。
設置環境や使用時間を考慮せずに導入すると、光熱費が想定以上に膨らむケースも。
ライフスタイルと断熱性に合わせ、必要な面積・運転時間を事前に計算しておきましょう。
- 電気式は初期費用が安く、部分的利用に最適。
- 温水式(ヒートポンプ)は熱効率が高く、広範囲使用で省エネ。
- 熱源別でランニングコストが月3,000円以上変わる。
後悔しない!明日からできる床暖房の賢い節約術
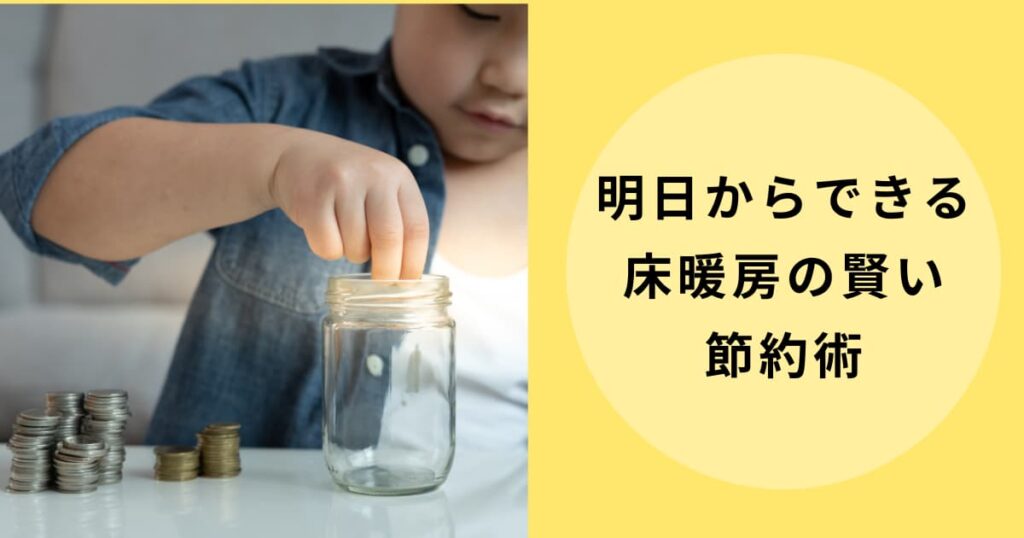
床暖房の使い方を少し工夫するだけで、光熱費は大きく変わります。今日からすぐに実践できる、効果的な節約術をご紹介します。
床暖房の省エネは「設定温度・時間・断熱」の3要素が鍵。
起動時はエアコンで補助し、安定後に床暖房に切り替えるのが効率的。
さらに、窓の断熱対策(遮熱カーテン・内窓・シート)を施すだけで、室内温度を2〜3℃高く維持できます。
温度維持の効率化で、年間電気代を最大約20%削減できます。
1. タイマー機能をフル活用する
最も基本的で効果的なのがタイマーの活用です。起床する30分前や帰宅する1時間前にオンになるように設定し、就寝時や外出時には自動でオフになるようにしましょう。生活リズムに合わせて設定することで、無駄な運転時間をなくし、快適さと節約を両立できます。
2. 設定温度を1℃だけ下げる
快適さを損なわない範囲で、設定温度を少し見直してみましょう。一般的に、設定温度を1℃下げるだけで、消費電力を約10%削減できると言われています。室温20℃~22℃程度でも、床からの輻射熱効果で十分に暖かく感じられます。ひざ掛けや厚手の靴下などを併用するのも良い方法です。
3. エアコンとの賢い併用術
部屋が冷え切っている状態から床暖房だけで暖めるのは、時間がかかり非効率です。まずはエアコンで部屋全体を素早く暖め、室温が安定したら床暖房に切り替えるか、低い設定温度で併用するのがおすすめです。それぞれの暖房器具の得意分野を活かすことで、効率よく快適な環境を作れます。
4. 窓の断熱対策で熱を逃がさない
暖房で温めた熱の約半分は、窓から逃げていくと言われています。厚手の断熱カーテンや遮熱カーテンに替えたり、二重窓や内窓を設置したりすることで、外からの冷気の侵入を防ぎ、室内の熱を閉じ込めることができます。これは床暖房の効率を格段に上げる、非常に効果的な対策です。
5. 床暖房パネルの上には物を置かない
床暖房の上にラグやカーペット、ソファなどの大きな家具を置くと、熱がうまく伝わらず暖房効率が著しく低下します。また、熱がこもることで床材を傷めたり、低温やけどの原因になったりする可能性もあります。床暖房のエリアには、できるだけ物を置かないように心がけましょう。

節電は「設備より使い方」です。
起床30分前・帰宅1時間前の自動オン設定を活用すれば、無駄な起動電力を抑えられます。
また、家具やラグを床暖房面に直接置くと熱がこもり、床材を痛める原因になります。
熱を均等に伝えるために床上20%は空ける配置を意識しましょう。
- 設定温度を1℃下げると消費電力約10%減(出典:資源エネルギー庁)。
- 窓からの熱損失は暖房エネルギーの約50%。
- タイマー・断熱・併用運転で年間最大20%の電気代削減が可能。
つけっぱなしの不安を解消!安全性とよくあるQ&A
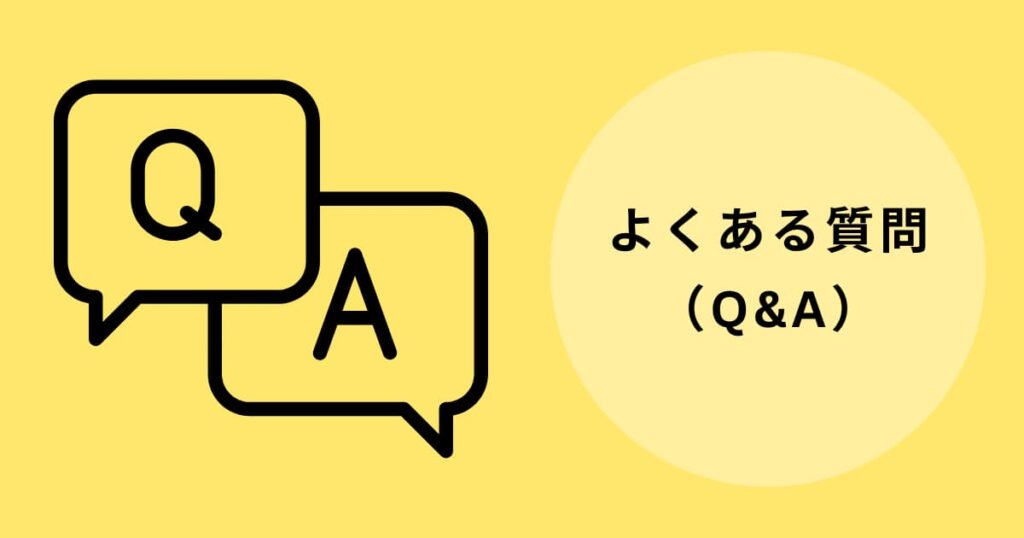
毎日使うものだからこそ、安全性に関する疑問や不安は解消しておきたいですよね。よくある質問にお答えします。
- 低温やけどの危険はないの?
-
長時間、同じ場所に肌が触れ続けると低温やけどのリスクがあります。特に電気式の床暖房は床面温度が高くなりやすいため注意が必要です。就寝時に布団を直接敷いて寝ることは避け、厚手のマットレスを使用しましょう。また、赤ちゃんやペットがいるご家庭では、長時間同じ場所で寝かせないように気をつけてあげてください。
- つけっぱなしによる火事や故障の心配は?
-
正常な使用状況であれば、火事の心配はほとんどありません。現在の床暖房は安全装置が内蔵されており、異常な温度上昇を感知すると自動で電源が切れる仕組みになっています。ただし、コントローラー周りにホコリが溜まると火災の原因になることもあるため、定期的にお手入れをしましょう。故障が疑われる場合は、速やかに専門業者に点検を依頼してください。
- ペット(犬・猫)がいるけど大丈夫?
-
ペットにとっても床暖房は快適ですが、注意が必要です。犬や猫は人間よりも低い温度で低温やけどを起こす可能性があります。ペットが自分で移動できない状態で長時間寝てしまわないよう、涼しい逃げ場(クールマットなど)を用意してあげましょう。また、コードをかじる癖があるペットの場合は、配線部分をカバーで保護するなどの対策も重要です。
まとめ
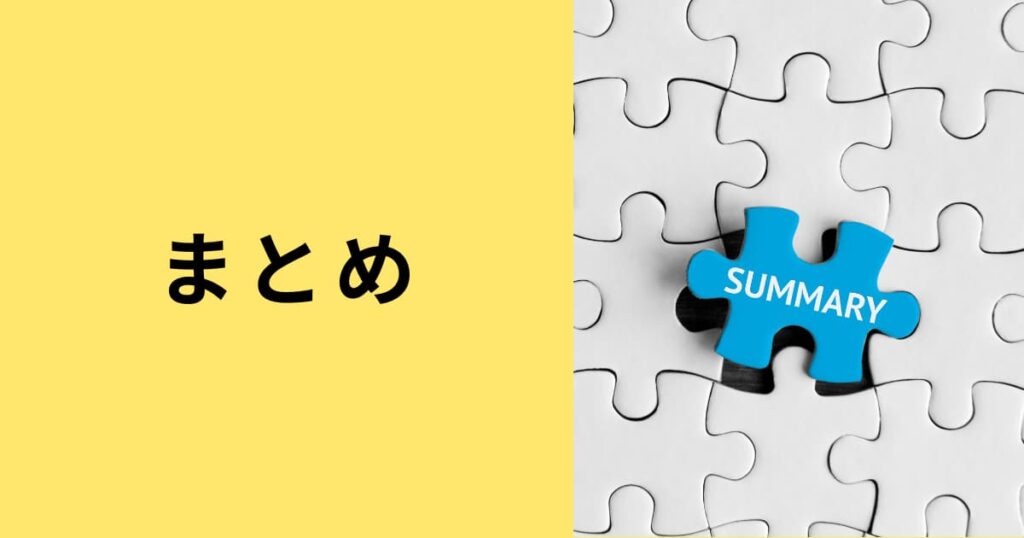
床暖房の「つけっぱなし」問題は、単一の正解があるわけではありません。あなたの家の断熱性能とライフスタイルを正しく理解し、それに合わせた使い方を選択することが、光熱費を抑えながら快適な冬を過ごすための最も重要な鍵となります。
この記事でお伝えしたポイントを参考に、ご自宅の床暖房の種類(電気式/温水式)を確認し、タイマー設定や断熱対策を見直してみてください。少しの工夫で、電気代への不安から解放され、心から暖かい冬の暮らしを手に入れることができるはずです。
出典URL
- 資源エネルギー庁|省エネポータル
- 消費者庁|家電安全ガイド
- 住宅性能評価・表示協会
- https://wiple-service.com/column/yukadanbo-denkidai-simulation-saving
- https://htb-energy.com/article/price/a73
- https://denki.docomo.ne.jp/article/45_floorheating.html
- https://enepi.jp/articles/383
- https://eneonedenki.net/topics/2942
- https://column.osakagas.co.jp/electricity/appliances/article/662
- https://dannetsu-takumi.com/contents/column/dannetsu-reform-beforeafter
- https://hosoda.co.jp/blog/column/floor-heating-pros-cons
- https://sumaimagine.com/6258
- https://halsa-inc.co.jp/blog/6851
- https://www.sunrefre.jp/sumutano/housing-equipment/7174/
- https://flie.jp/magazine/life-style/floorheating-leaveiton/
- https://www.pokara.co.jp/column/3499/
- https://www.daiken.jp/buildingmaterials/floorheating/columnrhc/004/